子どもを育てるうえで大切なのは、勉強や習い事だけではなく 「体験の豊かさ」 です。
学力や仕事力はもちろん、思いやりや自己肯定感といった「非認知能力」も、日常の体験を通じて育まれます。
この記事では、1歳の息子との実体験を交えながら、子どもの「生きる力」を伸ばす 5つの体験 について紹介します。
生きる力を育む「5つの体験」
子どもの「生きる力」を伸ばすために大切なのは以下の5つです。
- 自然体験
- 本物体験
- 没頭体験
- 失敗体験
- 成功体験
どれも特別なものではなく、日常生活の中で取り入れられるものばかりです。
1. 自然体験 五感を育てるチャンス
自然の中での体験は、子どもの五感を刺激します。
- 公園に行く:公園にはいろいろな植物があり、季節によってその植物が変化します。(子供と公園に行くようになって最近気づいたのですが)春になると、花が咲き、秋になると落ち葉や木のみで遊ぶことができます。子供って、木の実をたくさん集めたがりますよね。
- 虫に触ってみる :最近は、常に小さい図鑑を持ち歩いていて、名前のわからない虫は子供と一緒に図鑑で調べるようにしています。
- 朝日を見る:簡単なことのように見えて、私は忙しさのあまり見ることを忘れてしまうことがあります。意識すれば明日からできそうですね。
小さな体験でも、自然に触れることは子どもにとって大切な学びの場となります。
2. 本物体験 本物に触れることで心を動かす
子ども向けのコンサートに参加したり、本物の芸術や音楽に触れることで、感性を豊かにできます。
おもちゃではなく 「本物に触れる体験」 が子どもの心を大きく揺さぶります。
0歳の頃から息子と一緒にクラシックのコンサートに出かけています。0歳から参加できるクラシックコンサートは検索すると結構あります。私は、いつも「パフォーマンスグループココエ」さんのコンサートに参加しています。泣き声も演出の一つ!と言って下さり、子連れでも安心して参加することができます。子供向けの音楽が中心ですが、大人も十分楽しめます。コンサートが始まる前は、ギャン泣きだった息子も、始まると泣き止み聴き入っている様子でした。心地よいのか、そのまま寝てしまったこともありますが、、、
3. 没頭体験 集中力を育てる
子どもが時間を忘れて夢中になれる体験も大切です。
- 砂場遊び:現在2歳の息子は車が大好き。砂場でもおもちゃのショベルカーで砂を持ち上げ、ダンプカーに積むという作業をずっとやっていました。何度も何度も。大人はその楽しさを理解することは難しいですが、集中して遊んだ後は、気がすんだのか、やりきったからか、いつもは公園からなかなか帰らないのですがすんなりと言うことを聞きました。
- 絵を描く:2歳の息子は永遠に丸を描いています。色々な色で。でも集中している様子は見受けられます。また、最近は私が描いたアンパンマンやバイキンマンの顔を塗ることにハマっているようです。もちろんはみ出しますが、集中して色を塗っています。
- ブロック遊び:レゴブロック「デュプロ」がうちに届いてからは少しずつ1人でも遊べるようになってきました。家のようなものを作ったり、ブロックをひたすら高く積み上げたり週中有している様子が伺えます。レゴは想像力も豊かになりそうです。うまくいかなくてイライラして作ったものを壊している姿もありますが、気に入らなければ作り直せるところもレゴの良いところです。
「好きなことに没頭できる力」は、学習や仕事においても大きな財産になります。
4. 失敗体験 工夫する力を育てる
子どもは失敗を通じて工夫する力を育みます。
- ブロックを繋げる:なぜか違う種類のブロックを繋げようとすることがあります。また、つなげて長くしようとして途中で折れてしまうなんてこともあります。でも失敗を繰り返しながら、学び次に生かしている様子が伺えます。(時間はかかりますが)
- プラレールの線路を作る:うちの息子は児童館でよくプラレールを使って遊んでいます。児童館には違う種類のレールがあり物理的にどうしても繋がらないレールがあります。初めのうちはイライラして作ったものを壊していましたが、別の種類のレールはつながらないことが分かると、使い分けて遊ぶ姿が見られるようになりました。
- 積み木を積む:一定の高さまで積むと毎回倒れるので、毎回イライラしている様子でした。でも、積み木が崩れるのも面白い様子で、積んで崩れるまでを遊びとして捉えるようになり、機嫌が悪くなることは少なくなりました。
失敗は成長のチャンスです。親がポジティブに受け止めることで、子どもは失敗を恐れなくなります。
5. 成功体験 自信につながる
小さな成功体験を積み重ねることが、自信につながります。
- ペットボトルの蓋を閉める:最初から全部だとうまくいかないので、ある程度しめて途中で渡してできた体験を味わせるようにしました。
- 袋に物を入れる:子供がおもちゃを袋に入れても入れても袋の外側で、なかなか入らないことありますよね。また、チャックが開かなくて物が入れられず、イライラすることもありました。それも少しだけ手伝い、「できた」体験を味わせることができるようにしました。
「できた!」という気持ちは、子どもの自己肯定感を育てる大切な一歩です。
生きる力とは?
「生きる力」とは、偶然の出来事にどう対応し、どう工夫するかという力です。
文明が発達した現代では、便利になった一方で工夫する機会が減っているとも言われています。
子どもにさまざまな体験をさせることは、この「生きる力」を伸ばすことにつながります。
大人ができるサポート
- 子どもの話を急がず聞く姿勢
- 短所を「個性」として認める
- 自由に挑戦できる環境を用意する
親が子どもを信頼し、自由に工夫できる環境を与えることで、子どもは「わがまま」ではなく「自分らしく生きる力」を育てます。
まとめ
子どもの「生きる力」を伸ばすには、特別なお金や遠出は必要ありません。
日常の中でできる小さな体験が、子どもの非認知能力を育み、将来につながります。
とは言っても、日々忙しい中でそんな時間がない!と言う方も多いと思います。でも大人が少し意識することで子供にとってそれが素敵な体験につながることがあります。
ぜひ今日から、親子で一緒に「生きる力」を育てる体験を楽しんでみてください。
今回参考にした本はこちら↓
| 子どもの生きる力をのばす5つの体験 答えのない子育てで本当に大事なこと [ 汐見稔幸 ] 価格:1,540円(税込、送料無料) (2025/10/7時点) |

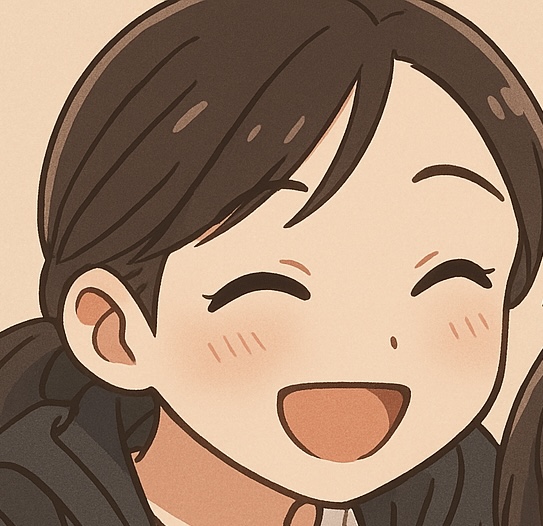
コメント